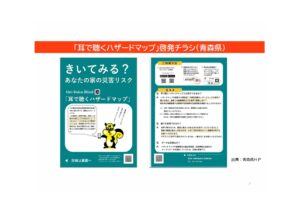2月25日令和7年第1回定例会での芥川 薫県議による一般質問を掲載させていただきます。
以下が内容です。
芥川 薫議員 質問:
民間の事業者が耳で聴くハザードマップを開発・運用していると承知しているが、県は避難対策を担う市町村と連携し、こうした新しい技術の活用も含め、障がい者などの特性に応じたきめ細かな災害情報の提供と防災に関する普及啓発の強化に取り組むべきである。
そこで、新たな防災戦略の策定を機に、要配慮者の防災意識の向上に向けた普及啓発にどのように取り組んでいくのか、見解を伺う。
知事 答弁:
県が現在、地震被害想定の見直しの一環で作成に取り組んでいる県民シナリオでは、特性の異なる要配慮者の皆様が地震発生時に直面する場面ととるべき行動などをとりまとめています。
例えば、地震発生時に、視覚障がいの方が自宅にいる場面では、周辺の物を叩いて助けを求めることのほか、予め、情報収集手段や支援者との連絡方法を確認しておくこと、地域の方々から協力が得られる関係を築いておくことなどの事前の備えも整理しています。
こうした要配慮者の皆様が直面する状況を、現時点で64の場面に整理しており、来年度開発予定の私の被害想定のほか、CG技術を活用した啓発映像や、かながわ防災パーソナルサポートに新たに設置する要配慮者専用ページ等に反映させます。
また、要配慮者の皆様の中には、電子媒体が苦手な方が少なくないとの意見もいただているため、必要な対応策を確認できる、要配慮者版地震防災チェックシートの作成にも取り組みたいと考えています。
さらに、災害情報の入手が困難な視覚障がい者の方への対応としては、音声の読み上げ機能を備えるように努めるほか、耳で聴くハザードマップなどの新しい技術の活用にも積極的に取り組んでいきます。
県は、新たな地震防災戦略に基づき、市町村とも連携し、要配慮者の特性を踏まえた普及啓発を強化し、防災意識の向上につなげてまいります。
芥川 薫議員 再質問:
要配慮者に対する防災の普及啓発の強化についてです。
要配慮者への普及啓発を進める考え方は分かった。県が取り組む様々な普及啓発の取組や、新たに作る要配慮者向けの啓発資料についても知ってもらうことが必要だと思うが、要配慮者や支援者に対する周知はどのように考えているのか。
知事 答弁:
要配慮者やその支援者に対する県の普及啓発の取組の周知についてのお尋ねでありました。
県は、地震被害想定の見直しや新たな地震防災戦略の検討にあたって、要配慮者ご本人や支援団体に対してヒアリングを重ねてきました。
その中で、県が現在進めている県民シナリオの内容や啓発資料について、評価をいただくとともに、当事者団体のネットワークの中で周知していきたいといった意見もいただいているところであります。
こうした、協力関係を築いた当事者の団体にご協力いただくほか、要配慮者一人ひとりの個別避難計画の作成に取り組む市町村と連携し、周知を徹底してまいります。
要望:
次に、要配慮者に対する防災の普及啓発の強化についてである。
答弁でもあったが、普及啓発に取り組んでいくとのことだった。答弁の中で、耳で聴くハザードマップの導入などの話もあったが、新しい技術を活用して、市町村と連携を図り、要配慮者が災害時に安全に避難ができるよう、スピード感をもって取り組んでいくよう要望する。