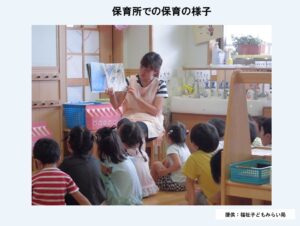2月26日令和7年第1回定例会での永田 磨梨奈県議による一般質問を掲載させていただきます。
以下が内容です。
永田 磨梨奈議員 質問:
こども誰でも通園制度の円滑な実施に向け、より多くの保育所で保育補助者の活用が進むよ
う、県として、どのように取り組んでいくのか、見解を伺う。
知事 答弁:
県では、令和8年度からの、こども誰でも通園制度の円滑な実施に向け、市町村と県の担当者による部会を設置し、意見交換を行っていますが、市町村からは「保育士が足りず、実施する保育所が見つからない」という切実な意見が寄せられています。
そのため、県独自の地域限定保育士試験など保育士を増やす取組とともに、保育士の負担を軽減し、就労継続を支援するため、掃除や給食の配膳など、資格が必要のない業務への保育補助者の活用も重要です。
国では、保育補助者の雇用への補助制度を設けていますが、保育所からは、「どういう人が来るのか分からず不安」などの理由から、その制度を活用して補助者を雇用する保育所は半数程度にとどまっています。
一方で、保育士を目指す学生や、社会貢献活動として子育て支援に関わりたいシニアの方からは、保育の現場を手伝いたいという声を多く伺っています。
そこで、保育士の負担軽減と、保育所の補助者活用の不安を解消するため、保育に関心のある学生、シニアの方などが「キッズサポーター」として保育補助者の業務を体験・学習するための費用を、令和7年度当初予算案に計上しました。
県では、この事業により、こども誰でも通園制度の円滑な実施に向けた保育補助者の活用が進むよう取り組んでまいります。
永田 磨梨奈議員 再質問:
それでは、1点、こども誰でも通園制度の円滑な実施に向けた保育補助者の活用について再質問をさせていただく。
「こども誰でも通園制度」は、0歳から2歳までの児童が利用できる制度であり、実施を検討している幼稚園などからは、4月時点では2歳である児童が、年度の途中で3歳の誕生日を迎えると補助が受けられなくなり、年度末まで預かることができないという課題があるといった声が届いている。
本制度をより多くの施設で実施してもらうためには、こうした課題をしっかり解決していくことが重要と考えますが、県としてどのように対応していくのか、見解を伺う。
知事 答弁:
この制度は、0歳児から2歳児までを対象としているため、3歳の誕生日を迎えると、園では補助が受けられなくなります。
幼稚園や保護者からは、「3歳になった年度末まで補助があると、年度途中で辞めずに利用ができ、4月から継続して幼稚園に入園できるため、この制度を活用しやすくなる」といった声を伺っています。
そのため、県としては、全てのこどもが本制度を利用して安心して幼稚園に通うことができるよう、現場の声をよく聴きながら、補助制度の見直しを国に求めていきます。
こういった地方の声を国に届けるためには、国政を担う方に対する大きな期待を抱きたいと思います。
要望:
こども誰でも通園制度の円滑な実施に向けた保育補助者の活用についてである。
今再質問した通り、様々な課題がまだまだ現場ではあるのだろうと考えている。机上で想定していること以外のことが現場ではあると思うので、幼稚園、認定こども園などでも「こども誰でも通園制度」を活用していただいている、そうした所の声というものをしっかり聞いていただきながら、知事も話していたが、県としてできることも考えてもらいながら、しっかりと国に制度の改善というものも求めていってほしいと思う。
幼稚園・認定こども園などで「こども誰でも通園制度」を活用するのは、地域の子育て世代に様々な子育て環境等を提供できる、選択肢を増やすことに繋がっていると思っている。
再質問したような「年度の途中で3歳の誕生日を迎えると補助が受けられなくなり、年度末まで預かることができない」といった課題等をしっかり解決することが、子どもたちの育ちの、そして子育て世代への様々な子育て環境の選択肢を提供することに繋がると考えているので、引き続き現場の課題に真摯に向き合い、令和8年度の本格実施に向けて、子どもたちの育ちにとって非常に重要な時期である乳児期を、質の高いものにするための一助となるような制度にしていただくことを要望する。